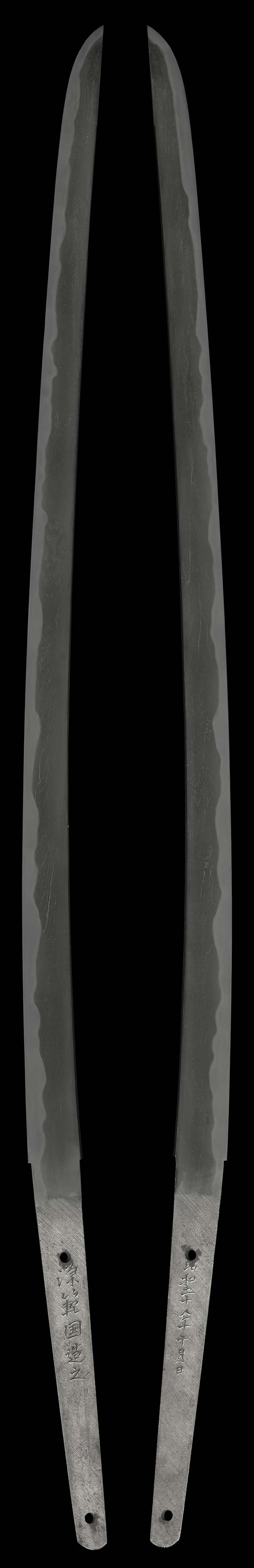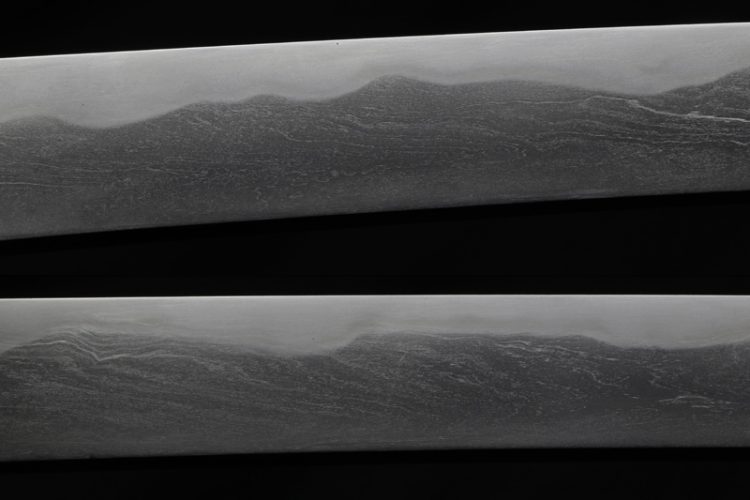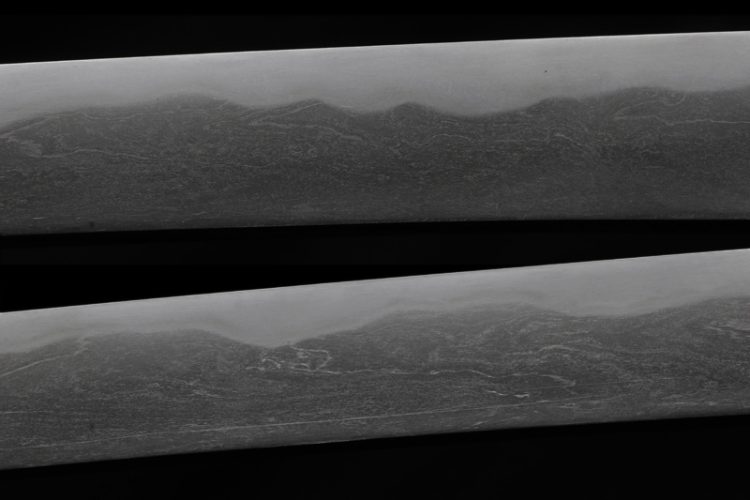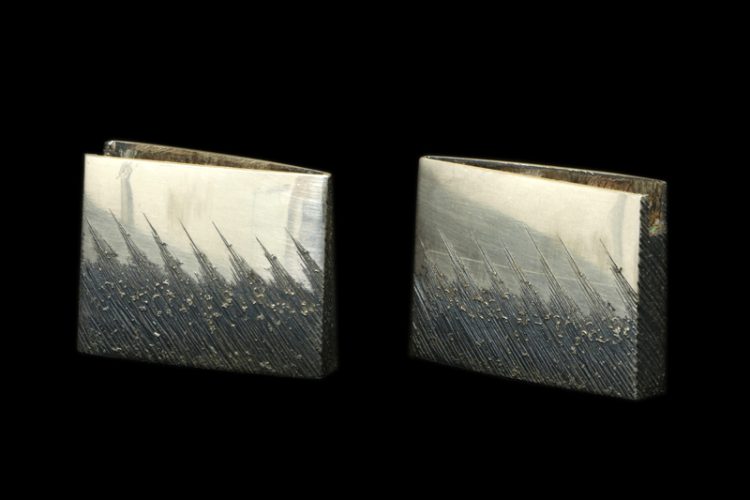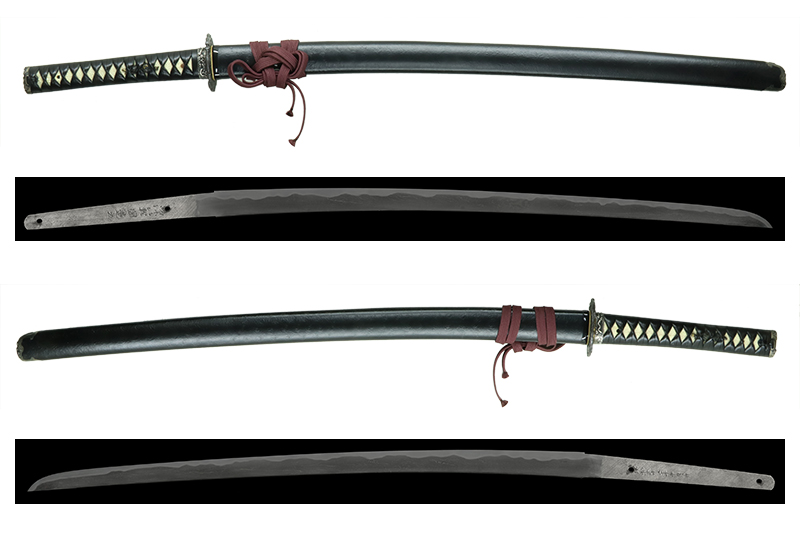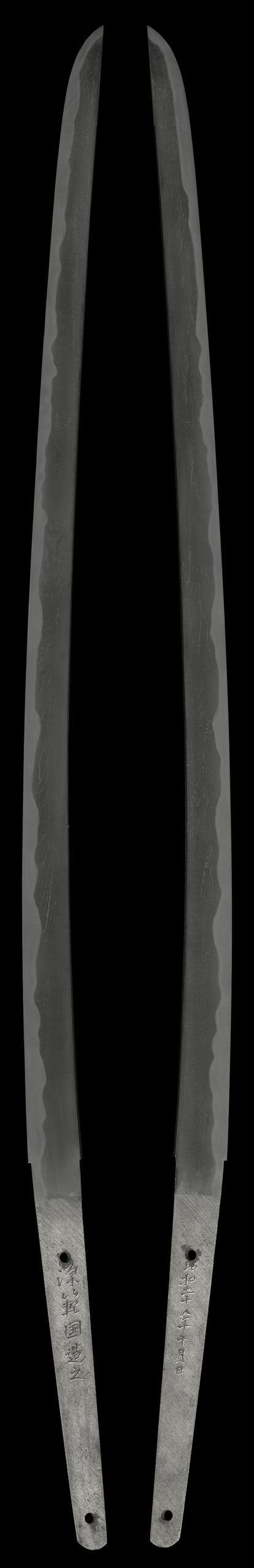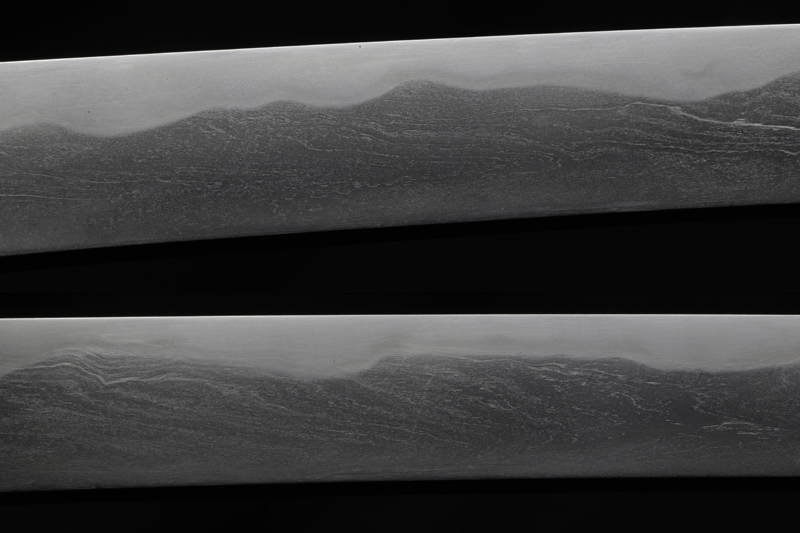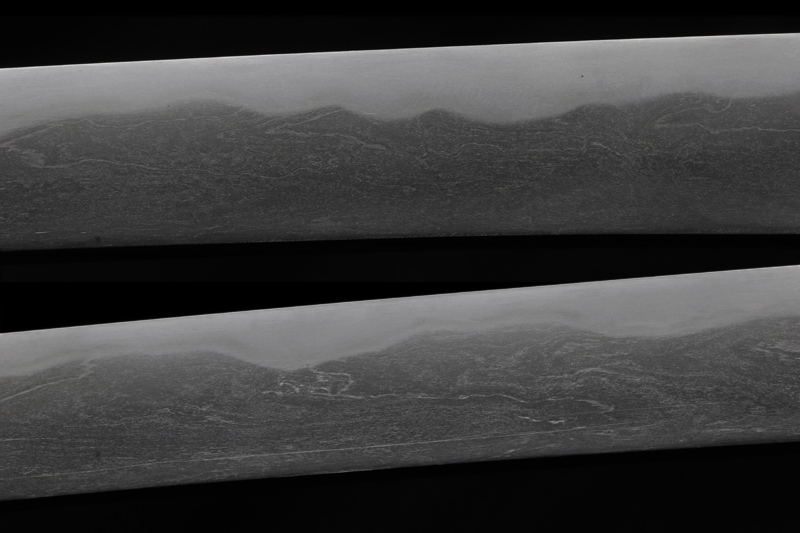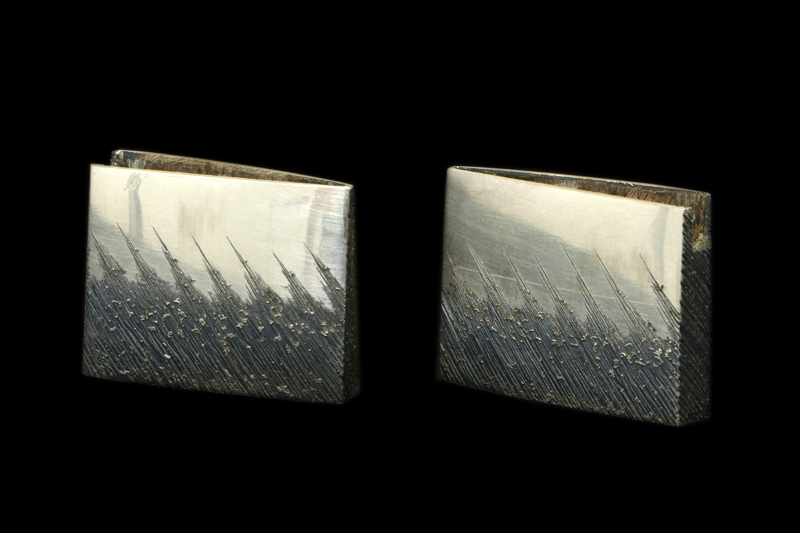説明
「刀姿 sword figure」
平造り庵棟、身幅広く重尋常、鳥居反りで中峰。茎は生で鑢目は筋違い、茎尻は栗尻。
「地鉄 jigane」
地鉄は板目肌が流れ柾となり、地沸厚く付き地景が入る。
「刃紋 hamon」
刃紋は沸出来の互の目乱れ、刃縁沸が付き砂流しかかり、刃中は金筋が働く。釯子は刃紋成りに入り焼き詰と成る。
「特徴 detailed」
源範國(本名:田中昇)は、徳島県で活動していた刀匠で、刀匠・水野正範の門人でした。範國は当初「則範」の銘を用いており、また、大業物として名高い鋭い刀を制作した源國次(本名:田中俊二)の父であり師でもあります。範國は自家製鋼による玉鋼を用い、優れた切れ味を持つ刀の鍛錬に専念しました。その高度な技術と探求心は、息子の國次へと受け継がれています。
本作は身幅が広く刃肉が薄い平造りの刀で、試斬に最適です。
元々は鑑賞用として特注された刀で、最近になって新たに拵が誂えられたものと考えられます。
そのため刀身のコンディションは非常に良く、拵もほぼ新品同様の状態です。
現代刀で平造りは珍しく、さらに身幅が広く重量バランスに優れた刀は滅多にありません。
ぜひこの機会にご入手ください。
Minamoto Norikuni (real name: Tanaka Noboru) was a swordsmith active in Tokushima Prefecture and a student of the swordsmith Mizuno Masanori. Norikuni initially signed his works as “Norinori” (則範). He was also the father and teacher of Minamoto Kunikazu (real name: Tanaka Shunji), famous for producing extremely sharp blades classified as ō-wazamono. Norikuni dedicated himself to forging blades with excellent cutting performance, using tamahagane produced through his own steel-making process. His high skill and spirit of craftsmanship were passed on to his son, Kunikazu.
This piece is a hira-zukuri style blade with a wide body and thin ha-niku, making it ideal for tameshigiri.
It appears to have originally been a specially ordered sword intended for appreciation, and only recently a new koshirae was commissioned for it.
Because of this, the blade is in excellent condition and the koshirae is essentially new.
Modern hira-zukuri swords are rare, and it is even more unusual to find one with a wide mihaba and excellent weight balance.
Do not miss this opportunity to acquire such a piece.
「拵 Koshirae」
縁頭と鐺は一作金具です。
ハバキ(habaki) :銀無垢一重の腰祐乗。
鍔(Tsuba) :鉄地団龍の図透かし。
縁頭(FuchiKashira) :銀地瑞雲に龍図。
目貫(menuki) :龍の図。
柄(Tsuka) :鮫は親粒が付き巻鮫。柄巻は牛表革黒の諸捻り巻。
鐺(kojiri) :銀地瑞雲に龍図。
鞘(Saya) :黒渦巻塗り。
「刀剣の状態 condition of blade」
研:概ね良好です。
傷:欠点に成るような傷は有りません。